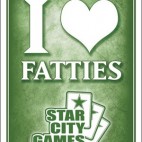「強く」「優しく」(美しく)
2018年5月10日
そのうちどっかに載せたい記事の草稿でした。
書いてから半年以上経ってしまったことを思い出して、改めて書き上げるつもりも無いので、このまま埋もれさせるくらいなら草稿のまま挙げます。
僕がマジックのジャッジでチームリーダーをやるに際して気を付けていることを紹介します。リーダーとして必要だと僕が考えて掲げている「強く」「優しく」「美しく」のうち、「強く」「優しく」とは何でどうバランスを取るかって内容です。
概要を書いていて、こんな内容を偉そうに晒すのに気が引けたから草稿で止まってたんだって思い出しました。恥ずかしくなったら消すかも。
*以下本文*
○リーダーシップ、難しい!
リーダーって難しいよね。
リーダーって難しいのに、何が難しくてどうすればいいのか多くの人は知らない、というより、知らないから難しく感じている。でもそれは、きちんと説明されることは少ないから知らないだけだ。きちんと要点を整理して訓練すれば、GPD2TL※を取るくらいならスーパーマンじゃなくてもなんとかなると、僕は考えている。
ここではGPD2TLを目指して小規模なチームリーダーの役割を果たすのに必要な観点を紹介するよ。
※「GP Day 2 Team Leader」レベル2ジャッジの中でグランプリの2日目のチームリーダーを担当できる資格。
○リーダーシップ、何故難しい?
リーダーの仕事はたくさんある。
計画を立てて、団結させて、模範を示して、連絡を取って、休憩を回して、問題に対応して、新人を教育して、、、しかもそのほとんどは、ただフロアジャッジをしてた頃には経験したことがないことばかりだ。
そんなのいきなり全部やるなんて、とても無理!
○リーダーシップ、何が難しい?
とても無理だから、整理しよう。
リーダーの仕事はたくさんあるけれど、その目的は究極的にはたったの2つなんだ。
「チームタスクに対する責任」
チームタスクを計画したり完遂させたり完成度を高めたりする。「チームタスクに対する責任」を重要視するリーダーは、解決型のリーダーと呼ばれる。解決型のリーダーは一般論として、チームが課題を抱えた危機的な状況に際してその真価を発揮する。チームメイトはそのとき、危機的な状況を誰か何とかしくれと、解決に導いてくれることをリーダーに期待する。
「チームメイトに対する責任」
チームメイトの意欲を高めたり体調を管理したり成長させたりする。上と同様に「チームメイトに対する責任」を重要視するリーダーは、調整型のリーダーと呼ばれる。調整型のリーダーは、チームが特別な課題を抱えていない平時にうまく機能する。チームメイトはそのとき、危機的な課題が無いときでも充実した環境を創出してくれることをリーダーに期待する。
チームとしての活動を終えて振り返ってみたとき、この2つの責任をきちんと果たせていれば、チームリーダーとして成功できたと言える。
未熟なリーダーにありがちなのは、このどちらかに傾倒してしまうことだ。「チームタスク」「チームメイト」どちらもしなきゃあならないのが「リーダー」のつらいところだな。
本当にグレイトなチームリーダーは常に両方を満たしてる。それが理想なんだとはわかっているが、そんなの一般人にはいきなりやれったって、やっぱり難しいよ。
○リーダーシップ、どう難しい?
難しいから、集中しよう。
一般人たる我らは、常に両方を満たすことを目指さず、その時々でどちらかに集中するんだ。
上で見た通り、リーダーに求められる行動はチームの状況に応じて変化する、そうだね?だったら、今がどんな状況なのかを意識して、解決型と調整型のどちらとして振る舞うかを考えよう。その時やらなければならない仕事をシンプルに大別するんだ。
イベントの中で、忙しい時間帯は解決型のリーダーとして振る舞い、チームタスクに立ち向かおう。例えば、朝のプレイヤーミーティングや、何かしらのトラブルが起きた時だね。課題を解決することに集中して、優先順位を付けて適切で明確な指示を出すことを意識しよう。
逆に、比較的忙しくない時間帯は調整型のリーダーとして振る舞い、チームメイトに向き合おう。イベントで特別な課題が起きていない大半の時間はこれにあたる。チームメイトの目標の達成度合いを確認したり、興味深いルーリングを共有したり、と言った具合だ。
筆者は大抵、意識の8割を解決型か調整型のどちらか片方に傾け、もう片方には2割を残す程度にしている。集中しろと言っておいて申し訳ないが、この意識を10割と0割まで倒してしまってはならないのは覚えておこう。仕事に熱中するあまり仲間に怒鳴り散らすリーダーや、一時的にでも仕事を完全に忘れるリーダーなんてダメだろ?
とはいえ、これからリーダーにチャレンジしようとしてる人にとって、解決型の行動と調整型の行動を片方ずつとはいえ両方を充分に行うことは、やはり簡単ではない。
○リーダーシップ、誰でも難しい?
簡単ではないから、任せよう。
チームメイトに適切な仕事を任せ、そして同時に権限も委譲しよう。
未熟なリーダーにありがちなのは、解決にせよ調整にせよ、リーダー自身がそれを行おうとすることだ。リーダーの役割はチームタスクとチームメイトに責任を持つことであり、リーダー自身がそれを行う必要なんてない。グレイトなチームリーダーはむしろ、積極的にチームメイトに委譲をする。
もしあなたが解決型の行動が得意であり、調整型の行動が苦手ということであれば、チームメイトの中で調整型の行動が得意な人に協力を求めよう。よくあるのは、中堅と新人をペアにして指導を任せたり、チーム内で伝達係を設定したり、などだ。
逆に、もしあなたが調整型の行動が得意であるなら、解決型の行動が得意な人に協力を求めよう。難しい仕事の半分程度をその人に任せて必要な人員を預け、自分は自分が対応できる範囲のみに集中しよう。
いずれにせよ気を付けなければならないのは、委譲する権限の範囲と、定期的な確認だ。委譲する権限の範囲は、狭すぎても広すぎても非効率で、不明瞭であれば混乱が起きてしまう。また権限を委譲しても、その仕事の責任はやはりあなたにある、いわゆる報連相で定期的な確認をしよう。
そうそう、チームリーダー自身もまたヘッドジャッジから仕事と権限を委譲された一人であることを忘れてはならない。チームリーダーとして委譲したチームメイトに期待することを、チームリーダーもヘッドジャッジに返そう。
○リーダーシップ、まだ難しい?
まとめ的な段落
GPD2TLへの申込みフォーム
(草稿のまま終わる)
書いてから半年以上経ってしまったことを思い出して、改めて書き上げるつもりも無いので、このまま埋もれさせるくらいなら草稿のまま挙げます。
僕がマジックのジャッジでチームリーダーをやるに際して気を付けていることを紹介します。リーダーとして必要だと僕が考えて掲げている「強く」「優しく」「美しく」のうち、「強く」「優しく」とは何でどうバランスを取るかって内容です。
概要を書いていて、こんな内容を偉そうに晒すのに気が引けたから草稿で止まってたんだって思い出しました。恥ずかしくなったら消すかも。
*以下本文*
○リーダーシップ、難しい!
リーダーって難しいよね。
リーダーって難しいのに、何が難しくてどうすればいいのか多くの人は知らない、というより、知らないから難しく感じている。でもそれは、きちんと説明されることは少ないから知らないだけだ。きちんと要点を整理して訓練すれば、GPD2TL※を取るくらいならスーパーマンじゃなくてもなんとかなると、僕は考えている。
ここではGPD2TLを目指して小規模なチームリーダーの役割を果たすのに必要な観点を紹介するよ。
※「GP Day 2 Team Leader」レベル2ジャッジの中でグランプリの2日目のチームリーダーを担当できる資格。
○リーダーシップ、何故難しい?
リーダーの仕事はたくさんある。
計画を立てて、団結させて、模範を示して、連絡を取って、休憩を回して、問題に対応して、新人を教育して、、、しかもそのほとんどは、ただフロアジャッジをしてた頃には経験したことがないことばかりだ。
そんなのいきなり全部やるなんて、とても無理!
○リーダーシップ、何が難しい?
とても無理だから、整理しよう。
リーダーの仕事はたくさんあるけれど、その目的は究極的にはたったの2つなんだ。
「チームタスクに対する責任」
チームタスクを計画したり完遂させたり完成度を高めたりする。「チームタスクに対する責任」を重要視するリーダーは、解決型のリーダーと呼ばれる。解決型のリーダーは一般論として、チームが課題を抱えた危機的な状況に際してその真価を発揮する。チームメイトはそのとき、危機的な状況を誰か何とかしくれと、解決に導いてくれることをリーダーに期待する。
「チームメイトに対する責任」
チームメイトの意欲を高めたり体調を管理したり成長させたりする。上と同様に「チームメイトに対する責任」を重要視するリーダーは、調整型のリーダーと呼ばれる。調整型のリーダーは、チームが特別な課題を抱えていない平時にうまく機能する。チームメイトはそのとき、危機的な課題が無いときでも充実した環境を創出してくれることをリーダーに期待する。
チームとしての活動を終えて振り返ってみたとき、この2つの責任をきちんと果たせていれば、チームリーダーとして成功できたと言える。
未熟なリーダーにありがちなのは、このどちらかに傾倒してしまうことだ。「チームタスク」「チームメイト」どちらもしなきゃあならないのが「リーダー」のつらいところだな。
本当にグレイトなチームリーダーは常に両方を満たしてる。それが理想なんだとはわかっているが、そんなの一般人にはいきなりやれったって、やっぱり難しいよ。
○リーダーシップ、どう難しい?
難しいから、集中しよう。
一般人たる我らは、常に両方を満たすことを目指さず、その時々でどちらかに集中するんだ。
上で見た通り、リーダーに求められる行動はチームの状況に応じて変化する、そうだね?だったら、今がどんな状況なのかを意識して、解決型と調整型のどちらとして振る舞うかを考えよう。その時やらなければならない仕事をシンプルに大別するんだ。
イベントの中で、忙しい時間帯は解決型のリーダーとして振る舞い、チームタスクに立ち向かおう。例えば、朝のプレイヤーミーティングや、何かしらのトラブルが起きた時だね。課題を解決することに集中して、優先順位を付けて適切で明確な指示を出すことを意識しよう。
逆に、比較的忙しくない時間帯は調整型のリーダーとして振る舞い、チームメイトに向き合おう。イベントで特別な課題が起きていない大半の時間はこれにあたる。チームメイトの目標の達成度合いを確認したり、興味深いルーリングを共有したり、と言った具合だ。
筆者は大抵、意識の8割を解決型か調整型のどちらか片方に傾け、もう片方には2割を残す程度にしている。集中しろと言っておいて申し訳ないが、この意識を10割と0割まで倒してしまってはならないのは覚えておこう。仕事に熱中するあまり仲間に怒鳴り散らすリーダーや、一時的にでも仕事を完全に忘れるリーダーなんてダメだろ?
とはいえ、これからリーダーにチャレンジしようとしてる人にとって、解決型の行動と調整型の行動を片方ずつとはいえ両方を充分に行うことは、やはり簡単ではない。
○リーダーシップ、誰でも難しい?
簡単ではないから、任せよう。
チームメイトに適切な仕事を任せ、そして同時に権限も委譲しよう。
未熟なリーダーにありがちなのは、解決にせよ調整にせよ、リーダー自身がそれを行おうとすることだ。リーダーの役割はチームタスクとチームメイトに責任を持つことであり、リーダー自身がそれを行う必要なんてない。グレイトなチームリーダーはむしろ、積極的にチームメイトに委譲をする。
もしあなたが解決型の行動が得意であり、調整型の行動が苦手ということであれば、チームメイトの中で調整型の行動が得意な人に協力を求めよう。よくあるのは、中堅と新人をペアにして指導を任せたり、チーム内で伝達係を設定したり、などだ。
逆に、もしあなたが調整型の行動が得意であるなら、解決型の行動が得意な人に協力を求めよう。難しい仕事の半分程度をその人に任せて必要な人員を預け、自分は自分が対応できる範囲のみに集中しよう。
いずれにせよ気を付けなければならないのは、委譲する権限の範囲と、定期的な確認だ。委譲する権限の範囲は、狭すぎても広すぎても非効率で、不明瞭であれば混乱が起きてしまう。また権限を委譲しても、その仕事の責任はやはりあなたにある、いわゆる報連相で定期的な確認をしよう。
そうそう、チームリーダー自身もまたヘッドジャッジから仕事と権限を委譲された一人であることを忘れてはならない。チームリーダーとして委譲したチームメイトに期待することを、チームリーダーもヘッドジャッジに返そう。
○リーダーシップ、まだ難しい?
まとめ的な段落
GPD2TLへの申込みフォーム
(草稿のまま終わる)
こんばんは、ずっと放置してました。
先日のBMO Vol.10において、デッキチェック※のチームリーダーとして少し変わったことをしましたので、そのレポートです。
※「JudgeApps」というフォーラムに投稿したレポートを、外出し用に加筆修正したものです。
※記事内で載せているSS画像は、レポート用のダミーイベントのものであり、実際のイベントのものではありません。
※プレイヤーが使用しているデッキを預かり、そのデッキが適正なものであると確認することを「デッキチェック」と呼びます。100人を超えるイベントではたいてい、そのデッキチェックやデッキリストの管理を担当するデッキチェックチームが構成されます。
◎目次
○エクセルを使ったプレイヤー情報の管理
○実際に使用したエクセルシート
・マスターリスト
・ラウンドシート
○エクセルを使う利点
・マスター番号がプレイヤー名の横に出せる
・デッキチェックの回数を記録して優先度を判断できる
・上位プレイヤー抽出を簡単にできる
・特定の対戦の抽出も簡単にできる
・追跡したいプレイヤーにも気付ける
○他のイベントで使えるの?
○文明の利器は使い得!
○それで、肝心のシートデータは?
○エクセルを使ったプレイヤー情報の管理
何をしたのかというと、BMペアリングで公開されるオンラインペアリング※を元に、エクセルを使ってプレイヤー情報を管理しました。
↓BMのオンラインペアリング。
http://onlinepairing.net/bmo/index.html
※該当イベントのスクショを撮り忘れました…
※ここ数年のマジックの大きなイベントでは、スマートフォンで対戦テーブル番号や対戦相手を確認できる「オンラインペアリング」が用いられています。
○実際に使用したエクセルシート
・マスターリスト
↓これです。
https://drive.google.com/open?id=1vIdgGsR37zZlhKYNBKeyTPDikCj89bnf
最初に作ります。
表示させていたのは、以下の内容です。
「プレイヤーのマスター番号」(最初にオンラインペアリングからコピペ)
「プレイヤーの名前」(最初にオンラインペアリングからコピペ)
「プレイヤーのデッキチェック回数」(ラウンドシートから自動入力)
「プレイヤーの勝ち点」(ラウンドシートから自動入力)
「プレイヤーの備考欄」(手動入力で自由記入)
デッキチェック回数や勝ち点は、後述のラウンドシートに入力されたものを引用して自動で最新情報へと更新されます。
今回はシートオール※を行わなかったので、第一ラウンド開始時の座席がそのままプレイヤーのマスター番号になっています。
※マジックの競技性の高いイベントでは、第一ラウンドの対戦組み合わせ発表の前に、開会挨拶や出欠席確認や物品配布回収のための「シートオール」がよく行われます。
備考欄は「スリーブ注意※」「デッキリスト61枚※」のように念のため気にしておきたい内容を書いていきます。
※マジックのイベントでは、裏や横から見て区別が付くようなスリーブを使うことはできません。故意でなくても、スリーブを長期間使って傷付いていたり別製造ロットのものと混ざっていたりすると、程度によっては交換してもらう必要があります。
※マジックの構築フォーマットでは、多くのプレイヤーはメインデッキを最少枚数である60枚で構築します。デッキリストに61枚のカードが登録されているのに61枚である旨が書かれていない場合、デッキリストの登録間違いが起こっているかもしれないと考えられます。
・ラウンドシート
↓各ラウンドに1枚、こんな感じになります。
https://drive.google.com/open?id=1iyHCr-d9dLGvWwuehWc-YAFUueDOnsIj
オンラインペアリングのページを全選択してコピペすれば、そのラウンドの対戦情報を一覧にできます。
表示させていたのは、以下の内容です。
「テーブル番号」(最初に手動入力)
「プレイヤーのマスター番号」(マスターリストから自動入力)
「プレイヤーの名前」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーの勝ち点」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーのデッキチェック回数」(マスターリストから自動入力)
「両プレイヤーの勝ち点の合計」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーの備考欄」(マスターリストから自動入力)
デッキチェックをしたら対戦は記録欄に「1」と入力します。そうするとマスターリストで全ラウンド分が集計されて、各ラウンドシートにデッキチェック回数として戻ってくる、という関数になっています。
○エクセルを使う利点
・マスター番号を対戦組み合わせに表示できる
実際にデッキチェックする手順において大きかったのはこれですね。
対戦組み合わせにプレイヤーの名前とともにマスター番号を表示させられます。
https://drive.google.com/open?id=1-jYH8KdR-B2H1d7vHH4vIS2aZ2XONuLh
これにより、普段のデッキチェックで行なっているような、名前からマスターリストの番号を探すという一手間※が無くなりました。
※普段は対戦組み合わせから名前を確認して、マスターリストで名前を探してマスター番号を確認して、デッキリストの束からマスター番号でプレイヤーのリストを探す、という手順が必要です。
GPデッキチェックチームを経験したことのある方ならわかると思いますが、イベントの参加人数が多ければ多いほど、この一手間を消せる意味は大きくなります。
(余談ですが、今回はデッキチェックチームのメンバーにはスマホでパソコンの表示画面をそのまま撮影してもらい、プレイヤー名やテーブル番号を書き写す手間まで無くしました。)
・デッキチェックの回数を記録して優先度を判断できる
対戦組み合わせにデッキチェック回数が一目で確認できるので、各プレイヤーへのデッキチェックの優先度を効率的に判断することができます。
https://drive.google.com/open?id=14hyQNUAVcHH0_PHI4zM3Qvtstj5NXLBf
「これまでにデッキチェックされていないプレイヤーの対戦」が一目でわかり、勝ち点などの情報と合わせることで上位対戦でチェックしたい対戦を効率的に探すことが可能です。
今回はヘッドジャッジからの指示でフロアジャッジの優先度を上げており、スイスラウンド中のデッキチェックは推奨回数の40回10%だけでした。それでも最終的なトップ8プレイヤーのうち7名をスイスラウンド中にデッキチェックすることができました。
・上位プレイヤー抽出を簡単にできる
エクセルを使う利点の1つが、リストからの抽出や並べ替えをできることです。
今回はこれを、デッキリストの60/15チェック※に利用しました。
※提出されたデッキリストが適正であるか確認することを、俗に「60/15チェック」と呼びます。マジックの構築フォーマットのデッキ枚数が多くのプレイヤーはメインデッキ60枚+サイドボード15枚で構成されているからです。
https://drive.google.com/open?id=1heQPSsbHwPAg8npqawK-Z2KJ1W7yp74V
60/15チェックは昨今軽視されがちで、上述の通りヘッドジャッジからもフロア優先と指示がありました。そこで少しでも効果的に60/15チェックを行えるよう、上位に残りそうな勝ち点の高いプレイヤー※を優先的にチェックを行いました。
※60/15チェックでデッキリストが不適正であった場合、その内容によってはプレイヤーに【ゲームの敗北】という重いペナルティが出てしまう可能性があります。イベント終盤で上位に残りそうなプレイヤーにこれが見付かるとダメージが大きくて胸が痛くなります。
マスターリストを操作して、勝ち点の高いプレイヤーだけを抽出して改めてマスター番号順に並べ替えることで、チェックするべきプレイヤーだけをストレスなくチェックすることができます。
・特定の対戦の抽出も簡単にできる
プレイヤーのマスターリストと同様、ラウンドシートの対戦一覧も抽出したり並び替えたりすることができます。
https://drive.google.com/open?id=1KTT3ORF4vy_2gw2XvLCAG5fV2etVKBNc
特に有用になるのは終盤のランダムテーブルになった際の上位対戦抽出で、対戦しているプレイヤーの勝ち点の合計で並べれば、もう紙のペアリングに線を引いて探す※必要はありません。
今回は、最終ラウンドまでランダムテーブルにはならなかったのでこの機能を使うことはなかったのですが、対応できるよう準備していました。
※マジックのイベントでは、基本的に対戦テーブル番号は順位順ですが、競技性の高いイベントでは終盤は無作為順になります。対戦結果によって上位入賞が左右される重要な対戦を見つけるのに、普段は紙の順位表と対戦組み合わせとを睨めっこして、重要な対戦に線を引いています。
・追跡したいプレイヤーにも気付ける
マスターリストの備考欄に入力した内容はラウンドシートからも見えるようになっており、デッキチェック対象を選ぶ際に参考にしていました。
https://drive.google.com/open?id=1yjQ3WSCkpEn82Jzl9pd1OlaVTLTgRAtj
具体的には、例えば注意が必要なスリーブの追跡が挙げられます。R1中に数名のフロアジャッジに依頼して全プレイヤーのスリーブを調査してもらい、「警告以上になりそう」「注意だけで終わりそう」に分けて報告してもらいました。
優先度の高い「警告以上」はすぐ次のラウンドで対応しましたが、「注意だけ」はとりあえず備考欄に記入するだけしておき、デッキチェックの対象を選択する際にラウンドシートで上位に出てきたら対応するようにしていました。
また、ここで「外スリーブをラウンドの間に交換してください」とお願いしたプレイヤーも、そう対応したことを記録したことを見て追跡することができました。
○他のイベントで使えるの?
今回のエクセルは、BMのオンラインペアリングに対応した形で組んであります。BMペアリングが使用されるイベントであればそのままで使うことができます。
ただBMペアリングは勝ち点などの表示する内容を調整することができるので、今回の内容以外を表示するよう設定される場合は引用がずれますので調整が必要です。
BMペアリング以外でも、対戦組み合わせが電子データとして共有されるのであれば、エクセル関数を扱える人ならそれ用にコピペから引用する関数を調整して使えると思います。
途中で書いた通り、プレイヤーの参加人数が多ければ多いほど情報整理を自動化するメリットは大きくなります。
逆に、参加者32人の店舗イベントで使ってもメリットは小さく準備するコストに合わないですね。
○文明の利器は使い得!
上で挙げた利点はすべて、ジャッジに充分な時間があればエクセルなしでも対応できるものです。
しかし我々にはそんな時間はありません。デッキチェックの準備はペアリング発表から迅速に進める必要があります。ラウンド進行中ずっと裏に隠れてマスターリストと睨めっこしているわけにはいけません。
そんな我々を補助するツールとして、今回のエクセルなどの電子機器は利用はとても有効なものでした。スマートフォンをはじめ、昨今の電子機器の発展は凄まじいものがあります。一昔前は考え付いても実現できなかったことが、今は実現できるようになってることも多いです。
ありがたく文明の利器を使わせてもらいましょう。
(余談ですが、今のこのレポートも喫茶店でスマートフォンと外付けキーボードで書いています。)
○それで、肝心のシートデータは?
↓こちらです。
ブランク版:
https://drive.google.com/open?id=16ELwHwEk2q4s9ZtfW3ekDne74L2T4CUx
使用例:
https://drive.google.com/open?id=16r8b7hacY_03z92MIx24S5wyun0FJw99
GoogleDriveにて共有してありますので、コピーしてご利用ください。
※ダウンロードしてエクセルで開いてください。Googleスプレッドシートだと動かない関数があるようです。
※意図的に関数を書き換える以外では、太字で説明してて枠が付いている箇所だけ入力してください。
使い方の不明点などありましたらコメントください。
皆さんからのフィードバックやブラッシュアップのアイデアをお待ちしています。
mtg2384@gmaill.com
先日のBMO Vol.10において、デッキチェック※のチームリーダーとして少し変わったことをしましたので、そのレポートです。
※「JudgeApps」というフォーラムに投稿したレポートを、外出し用に加筆修正したものです。
※記事内で載せているSS画像は、レポート用のダミーイベントのものであり、実際のイベントのものではありません。
※プレイヤーが使用しているデッキを預かり、そのデッキが適正なものであると確認することを「デッキチェック」と呼びます。100人を超えるイベントではたいてい、そのデッキチェックやデッキリストの管理を担当するデッキチェックチームが構成されます。
◎目次
○エクセルを使ったプレイヤー情報の管理
○実際に使用したエクセルシート
・マスターリスト
・ラウンドシート
○エクセルを使う利点
・マスター番号がプレイヤー名の横に出せる
・デッキチェックの回数を記録して優先度を判断できる
・上位プレイヤー抽出を簡単にできる
・特定の対戦の抽出も簡単にできる
・追跡したいプレイヤーにも気付ける
○他のイベントで使えるの?
○文明の利器は使い得!
○それで、肝心のシートデータは?
○エクセルを使ったプレイヤー情報の管理
何をしたのかというと、BMペアリングで公開されるオンラインペアリング※を元に、エクセルを使ってプレイヤー情報を管理しました。
↓BMのオンラインペアリング。
http://onlinepairing.net/bmo/index.html
※該当イベントのスクショを撮り忘れました…
※ここ数年のマジックの大きなイベントでは、スマートフォンで対戦テーブル番号や対戦相手を確認できる「オンラインペアリング」が用いられています。
○実際に使用したエクセルシート
・マスターリスト
↓これです。
https://drive.google.com/open?id=1vIdgGsR37zZlhKYNBKeyTPDikCj89bnf
最初に作ります。
表示させていたのは、以下の内容です。
「プレイヤーのマスター番号」(最初にオンラインペアリングからコピペ)
「プレイヤーの名前」(最初にオンラインペアリングからコピペ)
「プレイヤーのデッキチェック回数」(ラウンドシートから自動入力)
「プレイヤーの勝ち点」(ラウンドシートから自動入力)
「プレイヤーの備考欄」(手動入力で自由記入)
デッキチェック回数や勝ち点は、後述のラウンドシートに入力されたものを引用して自動で最新情報へと更新されます。
今回はシートオール※を行わなかったので、第一ラウンド開始時の座席がそのままプレイヤーのマスター番号になっています。
※マジックの競技性の高いイベントでは、第一ラウンドの対戦組み合わせ発表の前に、開会挨拶や出欠席確認や物品配布回収のための「シートオール」がよく行われます。
備考欄は「スリーブ注意※」「デッキリスト61枚※」のように念のため気にしておきたい内容を書いていきます。
※マジックのイベントでは、裏や横から見て区別が付くようなスリーブを使うことはできません。故意でなくても、スリーブを長期間使って傷付いていたり別製造ロットのものと混ざっていたりすると、程度によっては交換してもらう必要があります。
※マジックの構築フォーマットでは、多くのプレイヤーはメインデッキを最少枚数である60枚で構築します。デッキリストに61枚のカードが登録されているのに61枚である旨が書かれていない場合、デッキリストの登録間違いが起こっているかもしれないと考えられます。
・ラウンドシート
↓各ラウンドに1枚、こんな感じになります。
https://drive.google.com/open?id=1iyHCr-d9dLGvWwuehWc-YAFUueDOnsIj
オンラインペアリングのページを全選択してコピペすれば、そのラウンドの対戦情報を一覧にできます。
表示させていたのは、以下の内容です。
「テーブル番号」(最初に手動入力)
「プレイヤーのマスター番号」(マスターリストから自動入力)
「プレイヤーの名前」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーの勝ち点」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーのデッキチェック回数」(マスターリストから自動入力)
「両プレイヤーの勝ち点の合計」(オンラインペアリングから自動入力)
「プレイヤーの備考欄」(マスターリストから自動入力)
デッキチェックをしたら対戦は記録欄に「1」と入力します。そうするとマスターリストで全ラウンド分が集計されて、各ラウンドシートにデッキチェック回数として戻ってくる、という関数になっています。
○エクセルを使う利点
・マスター番号を対戦組み合わせに表示できる
実際にデッキチェックする手順において大きかったのはこれですね。
対戦組み合わせにプレイヤーの名前とともにマスター番号を表示させられます。
https://drive.google.com/open?id=1-jYH8KdR-B2H1d7vHH4vIS2aZ2XONuLh
これにより、普段のデッキチェックで行なっているような、名前からマスターリストの番号を探すという一手間※が無くなりました。
※普段は対戦組み合わせから名前を確認して、マスターリストで名前を探してマスター番号を確認して、デッキリストの束からマスター番号でプレイヤーのリストを探す、という手順が必要です。
GPデッキチェックチームを経験したことのある方ならわかると思いますが、イベントの参加人数が多ければ多いほど、この一手間を消せる意味は大きくなります。
(余談ですが、今回はデッキチェックチームのメンバーにはスマホでパソコンの表示画面をそのまま撮影してもらい、プレイヤー名やテーブル番号を書き写す手間まで無くしました。)
・デッキチェックの回数を記録して優先度を判断できる
対戦組み合わせにデッキチェック回数が一目で確認できるので、各プレイヤーへのデッキチェックの優先度を効率的に判断することができます。
https://drive.google.com/open?id=14hyQNUAVcHH0_PHI4zM3Qvtstj5NXLBf
「これまでにデッキチェックされていないプレイヤーの対戦」が一目でわかり、勝ち点などの情報と合わせることで上位対戦でチェックしたい対戦を効率的に探すことが可能です。
今回はヘッドジャッジからの指示でフロアジャッジの優先度を上げており、スイスラウンド中のデッキチェックは推奨回数の40回10%だけでした。それでも最終的なトップ8プレイヤーのうち7名をスイスラウンド中にデッキチェックすることができました。
・上位プレイヤー抽出を簡単にできる
エクセルを使う利点の1つが、リストからの抽出や並べ替えをできることです。
今回はこれを、デッキリストの60/15チェック※に利用しました。
※提出されたデッキリストが適正であるか確認することを、俗に「60/15チェック」と呼びます。マジックの構築フォーマットのデッキ枚数が多くのプレイヤーはメインデッキ60枚+サイドボード15枚で構成されているからです。
https://drive.google.com/open?id=1heQPSsbHwPAg8npqawK-Z2KJ1W7yp74V
60/15チェックは昨今軽視されがちで、上述の通りヘッドジャッジからもフロア優先と指示がありました。そこで少しでも効果的に60/15チェックを行えるよう、上位に残りそうな勝ち点の高いプレイヤー※を優先的にチェックを行いました。
※60/15チェックでデッキリストが不適正であった場合、その内容によってはプレイヤーに【ゲームの敗北】という重いペナルティが出てしまう可能性があります。イベント終盤で上位に残りそうなプレイヤーにこれが見付かるとダメージが大きくて胸が痛くなります。
マスターリストを操作して、勝ち点の高いプレイヤーだけを抽出して改めてマスター番号順に並べ替えることで、チェックするべきプレイヤーだけをストレスなくチェックすることができます。
・特定の対戦の抽出も簡単にできる
プレイヤーのマスターリストと同様、ラウンドシートの対戦一覧も抽出したり並び替えたりすることができます。
https://drive.google.com/open?id=1KTT3ORF4vy_2gw2XvLCAG5fV2etVKBNc
特に有用になるのは終盤のランダムテーブルになった際の上位対戦抽出で、対戦しているプレイヤーの勝ち点の合計で並べれば、もう紙のペアリングに線を引いて探す※必要はありません。
今回は、最終ラウンドまでランダムテーブルにはならなかったのでこの機能を使うことはなかったのですが、対応できるよう準備していました。
※マジックのイベントでは、基本的に対戦テーブル番号は順位順ですが、競技性の高いイベントでは終盤は無作為順になります。対戦結果によって上位入賞が左右される重要な対戦を見つけるのに、普段は紙の順位表と対戦組み合わせとを睨めっこして、重要な対戦に線を引いています。
・追跡したいプレイヤーにも気付ける
マスターリストの備考欄に入力した内容はラウンドシートからも見えるようになっており、デッキチェック対象を選ぶ際に参考にしていました。
https://drive.google.com/open?id=1yjQ3WSCkpEn82Jzl9pd1OlaVTLTgRAtj
具体的には、例えば注意が必要なスリーブの追跡が挙げられます。R1中に数名のフロアジャッジに依頼して全プレイヤーのスリーブを調査してもらい、「警告以上になりそう」「注意だけで終わりそう」に分けて報告してもらいました。
優先度の高い「警告以上」はすぐ次のラウンドで対応しましたが、「注意だけ」はとりあえず備考欄に記入するだけしておき、デッキチェックの対象を選択する際にラウンドシートで上位に出てきたら対応するようにしていました。
また、ここで「外スリーブをラウンドの間に交換してください」とお願いしたプレイヤーも、そう対応したことを記録したことを見て追跡することができました。
○他のイベントで使えるの?
今回のエクセルは、BMのオンラインペアリングに対応した形で組んであります。BMペアリングが使用されるイベントであればそのままで使うことができます。
ただBMペアリングは勝ち点などの表示する内容を調整することができるので、今回の内容以外を表示するよう設定される場合は引用がずれますので調整が必要です。
BMペアリング以外でも、対戦組み合わせが電子データとして共有されるのであれば、エクセル関数を扱える人ならそれ用にコピペから引用する関数を調整して使えると思います。
途中で書いた通り、プレイヤーの参加人数が多ければ多いほど情報整理を自動化するメリットは大きくなります。
逆に、参加者32人の店舗イベントで使ってもメリットは小さく準備するコストに合わないですね。
○文明の利器は使い得!
上で挙げた利点はすべて、ジャッジに充分な時間があればエクセルなしでも対応できるものです。
しかし我々にはそんな時間はありません。デッキチェックの準備はペアリング発表から迅速に進める必要があります。ラウンド進行中ずっと裏に隠れてマスターリストと睨めっこしているわけにはいけません。
そんな我々を補助するツールとして、今回のエクセルなどの電子機器は利用はとても有効なものでした。スマートフォンをはじめ、昨今の電子機器の発展は凄まじいものがあります。一昔前は考え付いても実現できなかったことが、今は実現できるようになってることも多いです。
ありがたく文明の利器を使わせてもらいましょう。
(余談ですが、今のこのレポートも喫茶店でスマートフォンと外付けキーボードで書いています。)
○それで、肝心のシートデータは?
↓こちらです。
ブランク版:
https://drive.google.com/open?id=16ELwHwEk2q4s9ZtfW3ekDne74L2T4CUx
使用例:
https://drive.google.com/open?id=16r8b7hacY_03z92MIx24S5wyun0FJw99
GoogleDriveにて共有してありますので、コピーしてご利用ください。
※ダウンロードしてエクセルで開いてください。Googleスプレッドシートだと動かない関数があるようです。
※意図的に関数を書き換える以外では、太字で説明してて枠が付いている箇所だけ入力してください。
使い方の不明点などありましたらコメントください。
皆さんからのフィードバックやブラッシュアップのアイデアをお待ちしています。
mtg2384@gmaill.com
ジャッジ褒章とイグザンプラープログラム
2016年10月6日コメント (1)
こんばんは、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第8回です。
(第5回と第6回のネタはあるのですが、時間が取れなくて文章にできずに積まれてます。)
さて今回は、先日ジャッジ褒章が自宅に届きましたので、そのお話をします。
ジャッジ褒章とは、認定ジャッジに配られるプロモーションカードです。
いくつかの方法で配られるものですが、かつて最も一般的だったのは、グランプリで運営に携わったジャッジ全員に一律に配られるというものでした。
しかしそれでは「仕事に対する報酬」になってしまって「貢献に対する褒章」ではありませんでした。また、グランプリに参加するジャッジにばかり配られてしまい、それよりも多く存在する各地区のコミュニティを支えているジャッジに対して配られることがほとんどありませんでした。
そのため、現在はその配り方は廃止されて別の方法で配られるようになっています。
現在、最も一般的なのは「イグザンプラープログラム」を通じて配られるものです。
http://blogs.magicjudges.org/exemplar/(※リンク先は英語)
「イグザンプラープラグラム」とは、ジャッジが他のジャッジにジャッジ褒章を贈るという活動です。具体的には、L2以上のジャッジが、ジャッジ褒章を贈りたい他のジャッジに対して推薦文を書いて送り、その推薦文に応じて実際にジャッジ褒章が郵送されてくるというものです。
書ける推薦文の数はジャッジのレベルや役割によって決まっており、例えばL2で特別な役割の無い僕なら1期(3ヵ月)で5人に対して書くことができます。
一方で受け取った推薦文の数によって贈られてくるジャッジ褒章の数も変わり、たくさん推薦文が集まれば複数セットのジャッジ褒章がもらえます。
そんなわけで、このイグザンプラープラグラムを通じて、公式的な表彰から個人的な感謝まで、様々な理由でジャッジ同士でジャッジ褒章を贈り合っています。
「特別な活動で地域に貢献している」
「参考になるレポートとして上げた」
「一緒に活動する中で勉強になった」
「困ったときに助けてもらえた」
…などなどなど。
これにより、かつてのようにグランプリに参加していれば一律に同じ数をもらえるということはなくなりました。しかしその分、他のジャッジに良い影響を与えた人や、イベント以外で特別な活動をした人が、その分だけ表彰してもらえるようになりました。
また、それらの推薦文は全てのジャッジから読めるようになっており、それぞれの持っている良い点を紹介する機会にもなっています。知り合いのジャッジが推薦されているのを読んで共感したり、今まで気付かなかった新しい一面を発見したりすることができるのは、グランプリで一律に配られていた頃にはなかった楽しみです。
一方で、こう書くと特別なことをしている一部のジャッジしか推薦がもらえないのではないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。
特にL1ジャッジに関しては、推薦文を書ける数にはL1ジャッジに対してのみ使える枠があり、贈られている推薦文の4割以上がL1ジャッジに対してものです。そのため、グランプリに参加しないL1ジャッジも、地元の身近なL2ジャッジに活動をアピールできれば推薦をもらえるチャンスが充分にあります。
全員に行き渡るというわけにはいきませんが、グランプリに参加しなければほぼジャッジ褒章を貰うことができなかった頃に比べれば、大きな変化でしょう。
というわけで今週はジャッジ褒章とイグザンプラープログラムについての紹介でした。
君もジャッジ褒章が欲しい?
まずはL1ジャッジになりましょう!
ジャッジに興味がある方はコメントかメールでお気軽にご連絡下さい。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○10/08土 PPTQ霊気紛争-フェイズ新瑞橋店
○10/09日 PPTQ霊気紛争-BIGMAGIC名古屋店
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第8回です。
(第5回と第6回のネタはあるのですが、時間が取れなくて文章にできずに積まれてます。)
さて今回は、先日ジャッジ褒章が自宅に届きましたので、そのお話をします。
ジャッジ褒章とは、認定ジャッジに配られるプロモーションカードです。
いくつかの方法で配られるものですが、かつて最も一般的だったのは、グランプリで運営に携わったジャッジ全員に一律に配られるというものでした。
しかしそれでは「仕事に対する報酬」になってしまって「貢献に対する褒章」ではありませんでした。また、グランプリに参加するジャッジにばかり配られてしまい、それよりも多く存在する各地区のコミュニティを支えているジャッジに対して配られることがほとんどありませんでした。
そのため、現在はその配り方は廃止されて別の方法で配られるようになっています。
現在、最も一般的なのは「イグザンプラープログラム」を通じて配られるものです。
http://blogs.magicjudges.org/exemplar/(※リンク先は英語)
「イグザンプラープラグラム」とは、ジャッジが他のジャッジにジャッジ褒章を贈るという活動です。具体的には、L2以上のジャッジが、ジャッジ褒章を贈りたい他のジャッジに対して推薦文を書いて送り、その推薦文に応じて実際にジャッジ褒章が郵送されてくるというものです。
書ける推薦文の数はジャッジのレベルや役割によって決まっており、例えばL2で特別な役割の無い僕なら1期(3ヵ月)で5人に対して書くことができます。
一方で受け取った推薦文の数によって贈られてくるジャッジ褒章の数も変わり、たくさん推薦文が集まれば複数セットのジャッジ褒章がもらえます。
そんなわけで、このイグザンプラープラグラムを通じて、公式的な表彰から個人的な感謝まで、様々な理由でジャッジ同士でジャッジ褒章を贈り合っています。
「特別な活動で地域に貢献している」
「参考になるレポートとして上げた」
「一緒に活動する中で勉強になった」
「困ったときに助けてもらえた」
…などなどなど。
これにより、かつてのようにグランプリに参加していれば一律に同じ数をもらえるということはなくなりました。しかしその分、他のジャッジに良い影響を与えた人や、イベント以外で特別な活動をした人が、その分だけ表彰してもらえるようになりました。
また、それらの推薦文は全てのジャッジから読めるようになっており、それぞれの持っている良い点を紹介する機会にもなっています。知り合いのジャッジが推薦されているのを読んで共感したり、今まで気付かなかった新しい一面を発見したりすることができるのは、グランプリで一律に配られていた頃にはなかった楽しみです。
一方で、こう書くと特別なことをしている一部のジャッジしか推薦がもらえないのではないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。
特にL1ジャッジに関しては、推薦文を書ける数にはL1ジャッジに対してのみ使える枠があり、贈られている推薦文の4割以上がL1ジャッジに対してものです。そのため、グランプリに参加しないL1ジャッジも、地元の身近なL2ジャッジに活動をアピールできれば推薦をもらえるチャンスが充分にあります。
全員に行き渡るというわけにはいきませんが、グランプリに参加しなければほぼジャッジ褒章を貰うことができなかった頃に比べれば、大きな変化でしょう。
というわけで今週はジャッジ褒章とイグザンプラープログラムについての紹介でした。
君もジャッジ褒章が欲しい?
まずはL1ジャッジになりましょう!
ジャッジに興味がある方はコメントかメールでお気軽にご連絡下さい。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○10/08土 PPTQ霊気紛争-フェイズ新瑞橋店
○10/09日 PPTQ霊気紛争-BIGMAGIC名古屋店
フロアルールの更新とディールシャッフル
2016年9月29日
こんばんは、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第7回です。
(第5回と第6回のネタはあるのですが、時間が取れなくて文章にできずに積まれてます。)
さて今回は、先日フロアルールの更新が発表されましたので、そのお話をします。
そもそもフロアルールとは何かというと、イベントに関するルールです。
マジックには、ゲーム内のルールである『総合ルール』の他に、ゲーム内に限らずイベントがどのように行われるべきかというルールがあり、俗に『フロアルール』と呼ばれています。
例えば、「ラウンドの終了時間が来たときに対戦の決着がついていなかったらどうするか」は、総合ルールには書いてありません、それはゲームの外のことです。しかし実際にイベントを進行するためには決めておかなければなりません。そこで、そのようなイベントに関することはフロアルールで定められています。
これらのルールが更新されるタイミングは決まっており、楽しい楽しいプレリリース週明けの月曜日に発表され、それらは発売日(つまり明日!)から適用されることになります。
(ちなみに、英語で出たアナウンスを即日中に日本語に翻訳してくれる凄い人もいます。
http://jg0xol.diarynote.jp/201609270522202316/)
フロアルールの更新は、イベントの進行手順や違反への対応などプレイヤーが知る必要の無いことも多いですが、今回はプレイヤーにも知って気を付けてほしい変更がありました。
それは、ディールシャッフルに関してです。
ディールシャッフルとは、別名でパイルシャッフルや○山切りなどとも呼ばれる、いくつかの山に分けて1枚ずつカードを配っていくシャッフルです。他のシャッフル方法と比べてスリーブを傷付けにくいという利点があり、使用しているプレイヤーも多いかと思います。
しかしこのディールシャッフルに関して、以下のような変更が加えられます。
・ディールシャッフルだけでは充分な無作為化とは認められなくなりました。
・ディールシャッフルは切り直し1回につき1回しか行ってはならなくなりました。
2017年1月に更に変更されました。2017年1月時点でのルールは以下の通りです。
ディールシャッフルは1ゲームにつき1回しか行ってはならなくなりました。
明確な理由は発表されてはいませんが、以下のような理由だと言われています。
・実際はカードを並べ替えているだけなので容易に積み込みができてしまう。
・何度も繰り返すと非常に時間がかかってしまう/時間稼ぎができてしまう。
・無作為化の手段としては時間がかかる割に効果が小さい。
ディールシャッフルが、無作為化の手段として対時間効果が小さいというのは、意外と感じる人もいるかと思います。
デッキを「均質化」するのであれば効果的です。例えば、サイドインしたカードをデッキの一番上にまとめて積んでからディールシャッフルを始めれば、デッキ内に綺麗にバラバラに配置され、よく混ざっているように見えるでしょう。
しかしそれは、MTGで求められている「無作為化」とは違います。無作為化とは、デッキの中の並びやカードの位置が全く分からない状態です。上の例で、サイドインしたカードがデッキ内に綺麗にバラバラに配置されている状態は、「無作為化」されているとは認められません。
ディールシャッフルは、普通に行うとただ規則的に並び替えるだけであり、配る山の順番などで工夫をしてもある程度の規則性は残ってしまいます。また、後述で推奨されているファローシャッフルに比べて同じ時間で動かせるカードの枚数も少ないです。無作為化の手段として意味が無いとまでは言いませんが、時間がかかる割に非常に効果が小さいと言えます。
ジャッジ関係者のフォーラムでは、元L5の偉いジャッジが「あれはシャッフルじゃない!数えてるだけ!“パイルシャッフル”と呼ぶのをやめて“パイルカウンティング”と名付けよう!」なんて言っているくらいです。
というわけで、ここからはディールシャッフル改めパイルカウンティングと呼ぶことにします。
一方で、パイルカウンティングを行うこと自体は、悪いことではありません。
無作為化の手段としては効果が小さくても、デッキのカード枚数やスリーブの状態を確認する手段としては有効なものです。それらを目的として、対戦を始める前に行うことは、むしろ良いことでしょう。
良くないのは、パイルカウンティングを無作為化の手段として繰り返すことです。
デッキ枚数やスリーブの状態は一度確認できれば充分で、短期間に何度も繰り返し行う必要はありません。無作為化の手段としては他にもっと効果的な方法があるので、限りある対戦時間は大切に使ってほしい、ということです。
ならば、どのようなシャッフルを行えばよいのでしょうか。
詳しくは、少し古いですが↓の動画がとてもわかりやすいので観てください。
https://www.youtube.com/watch?v=isfHlD-qc8Q
シャッフルを行う際のポイントは、以下の通りです。
・ファローシャッフルは繰り返すことでカードの並びも場所もわからなくなるのでメインに使う。
・ファローシャッフルはデッキの一番上や一番下が残らないようにずらして入れる。
・ファローシャッフル数回ごとにヒンズーシャッフルを挟んで更に無作為性を高める。
この方法でシャッフルを行えば、効果的な無作為化ができます。
目安としては、ファローシャッフルを最低10回以上、できれば15回以上繰り返してください。
それでも、パイルカウンティングを2回行うよりも、早く終わるでしょう。
というわけで、この日記を読んでくれた皆さんはこの機会に、今までよりも少しシャッフルに気を付けてみてください。
とはいえ、長く続けてきた慣習を新しくするには、まだしばらく時間がかかることでしょう。
もし、あなたの身近に“パイルカウンティング”を繰り返しているプレイヤーがいたら、優しく教えてあげてください。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
おっと、その前に日記を書いていない分を書かなければ…
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○10/01土 PPTQ霊気紛争-アドバンテージ上前津
http://www.advantagetcg.jp/product/26814
○10/02日 PPTQ霊気紛争-イエローサブマリン名古屋GAMESHOP
http://www.yellowsubmarine.co.jp/taikai/taikai_057.htm
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第7回です。
(第5回と第6回のネタはあるのですが、時間が取れなくて文章にできずに積まれてます。)
さて今回は、先日フロアルールの更新が発表されましたので、そのお話をします。
そもそもフロアルールとは何かというと、イベントに関するルールです。
マジックには、ゲーム内のルールである『総合ルール』の他に、ゲーム内に限らずイベントがどのように行われるべきかというルールがあり、俗に『フロアルール』と呼ばれています。
例えば、「ラウンドの終了時間が来たときに対戦の決着がついていなかったらどうするか」は、総合ルールには書いてありません、それはゲームの外のことです。しかし実際にイベントを進行するためには決めておかなければなりません。そこで、そのようなイベントに関することはフロアルールで定められています。
これらのルールが更新されるタイミングは決まっており、楽しい楽しいプレリリース週明けの月曜日に発表され、それらは発売日(つまり明日!)から適用されることになります。
(ちなみに、英語で出たアナウンスを即日中に日本語に翻訳してくれる凄い人もいます。
http://jg0xol.diarynote.jp/201609270522202316/)
フロアルールの更新は、イベントの進行手順や違反への対応などプレイヤーが知る必要の無いことも多いですが、今回はプレイヤーにも知って気を付けてほしい変更がありました。
それは、ディールシャッフルに関してです。
ディールシャッフルとは、別名でパイルシャッフルや○山切りなどとも呼ばれる、いくつかの山に分けて1枚ずつカードを配っていくシャッフルです。他のシャッフル方法と比べてスリーブを傷付けにくいという利点があり、使用しているプレイヤーも多いかと思います。
しかしこのディールシャッフルに関して、以下のような変更が加えられます。
・ディールシャッフルだけでは充分な無作為化とは認められなくなりました。
・
2017年1月に更に変更されました。2017年1月時点でのルールは以下の通りです。
ディールシャッフルは1ゲームにつき1回しか行ってはならなくなりました。
明確な理由は発表されてはいませんが、以下のような理由だと言われています。
・実際はカードを並べ替えているだけなので容易に積み込みができてしまう。
・何度も繰り返すと非常に時間がかかってしまう/時間稼ぎができてしまう。
・無作為化の手段としては時間がかかる割に効果が小さい。
ディールシャッフルが、無作為化の手段として対時間効果が小さいというのは、意外と感じる人もいるかと思います。
デッキを「均質化」するのであれば効果的です。例えば、サイドインしたカードをデッキの一番上にまとめて積んでからディールシャッフルを始めれば、デッキ内に綺麗にバラバラに配置され、よく混ざっているように見えるでしょう。
しかしそれは、MTGで求められている「無作為化」とは違います。無作為化とは、デッキの中の並びやカードの位置が全く分からない状態です。上の例で、サイドインしたカードがデッキ内に綺麗にバラバラに配置されている状態は、「無作為化」されているとは認められません。
ディールシャッフルは、普通に行うとただ規則的に並び替えるだけであり、配る山の順番などで工夫をしてもある程度の規則性は残ってしまいます。また、後述で推奨されているファローシャッフルに比べて同じ時間で動かせるカードの枚数も少ないです。無作為化の手段として意味が無いとまでは言いませんが、時間がかかる割に非常に効果が小さいと言えます。
ジャッジ関係者のフォーラムでは、元L5の偉いジャッジが「あれはシャッフルじゃない!数えてるだけ!“パイルシャッフル”と呼ぶのをやめて“パイルカウンティング”と名付けよう!」なんて言っているくらいです。
というわけで、ここからはディールシャッフル改めパイルカウンティングと呼ぶことにします。
一方で、パイルカウンティングを行うこと自体は、悪いことではありません。
無作為化の手段としては効果が小さくても、デッキのカード枚数やスリーブの状態を確認する手段としては有効なものです。それらを目的として、対戦を始める前に行うことは、むしろ良いことでしょう。
良くないのは、パイルカウンティングを無作為化の手段として繰り返すことです。
デッキ枚数やスリーブの状態は一度確認できれば充分で、短期間に何度も繰り返し行う必要はありません。無作為化の手段としては他にもっと効果的な方法があるので、限りある対戦時間は大切に使ってほしい、ということです。
ならば、どのようなシャッフルを行えばよいのでしょうか。
詳しくは、少し古いですが↓の動画がとてもわかりやすいので観てください。
https://www.youtube.com/watch?v=isfHlD-qc8Q
シャッフルを行う際のポイントは、以下の通りです。
・ファローシャッフルは繰り返すことでカードの並びも場所もわからなくなるのでメインに使う。
・ファローシャッフルはデッキの一番上や一番下が残らないようにずらして入れる。
・ファローシャッフル数回ごとにヒンズーシャッフルを挟んで更に無作為性を高める。
この方法でシャッフルを行えば、効果的な無作為化ができます。
目安としては、ファローシャッフルを最低10回以上、できれば15回以上繰り返してください。
それでも、パイルカウンティングを2回行うよりも、早く終わるでしょう。
というわけで、この日記を読んでくれた皆さんはこの機会に、今までよりも少しシャッフルに気を付けてみてください。
とはいえ、長く続けてきた慣習を新しくするには、まだしばらく時間がかかることでしょう。
もし、あなたの身近に“パイルカウンティング”を繰り返しているプレイヤーがいたら、優しく教えてあげてください。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
おっと、その前に日記を書いていない分を書かなければ…
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○10/01土 PPTQ霊気紛争-アドバンテージ上前津
http://www.advantagetcg.jp/product/26814
○10/02日 PPTQ霊気紛争-イエローサブマリン名古屋GAMESHOP
http://www.yellowsubmarine.co.jp/taikai/taikai_057.htm
ジャッジカンファレンスに参加してきました
2016年9月8日
こんばんは、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第4回です。
さて今回は、先週末の土曜日に名古屋の大須で行われたジャッジカンファレンスというものに参加してきましたので、そのお話をします。
ジャッジカンファレンスとは、ざっくり言えばジャッジの勉強会です。
ジャッジがイベント運営以外で複数人が集まり、ノウハウを共有するためのセミナーやコミュニティ形成のための会議などを行うものです。
さてこのジャッジカンファレンス、ここ数年でその内容が大きく変化しています。
日本でジャッジカンファレンスが行われ始めたのは3年ほど前で、主にグランプリに際して行われてきました。しかしそのため参加できるのはグランプリに来ているジャッジだけであり、地方のコミュニティを支えてくれているけれどグランプリには来ない・来られないジャッジが参加できないという問題を抱えていました。
そこで今年は、できるだけ多くのジャッジが参加できるように変化しました。大きなイベントにジャッジが遠征するではなく、地域ごとにそこに住むジャッジが集まれるよう、日本をいくつものエリアに区切って行うエリアカンファレンスという形式になりました。
今回は東海エリアカンファレンスとして、愛知・岐阜・三重からジャッジ約15名が名古屋大須に集まったというわけです。
そんな東海エリアカンファレンスは、まったりとした雰囲気で進行していました。
昨年までは、競技性の高いイベントを前提としたテーマが多かったのですが、今年は地元のレベル1ジャッジを主眼としています。そのため、地域のジャッジの活動状況を確認したり、地元でジャッジを増やすための方策を考えたりといったテーマで話し合いが行われました。
(もしこの日記を読んでジャッジに興味を持ってくれた人がいたら声をかけてくださいね!)
地域のジャッジが一同に会することは実はあまりなく、レベル1ジャッジだと他の地区のジャッジと交流が無いこともありますが、今回がレベル1ジャッジ同士の交流の場にもなっていたようです。
いつもジャッジとしてお世話になっているカードショップの店員さんもレベル1ジャッジとして参加していたのでちょっぴり緊張したり。
僕自身も久しぶりに会った人や初めて会った人がいて、またジャッジとしての親交の輪を広げることができました。
また、カンファレンスの参加者には、ジャッジ褒章フォイルも配布されました。
滅びはまだ4枚揃っていなかったので結構嬉しい。
そしてジャッジカンファレンスが終わったら、今回のために名古屋を訪れた日本の地域コーディネーター(日本のジャッジのまとめ役)を連れて4人で鶴舞のステーキ屋に向かいます。
STEAKEYE【ステーキアイ】
http://www.steak-eye.com/index.html
http://jouhou.nagoya/steak-eye/
看板料理となっている熟成肉のステーキは、脂が弾ける派手なステーキではなく、しっとりとした肉の旨みをゆっくり味わうことのできる上品な仕上がり。
アラカルトメニューも丁寧な仕事で悉くが美味く、何を頼んでも外れません。
僕のお気に入りは、野菜と肉の旨みが見事に調和した優しくも力強いポトフと、肉とガーリックのパンチがガツンと腹に響くガーリックライスです。
ぜひ一度ご賞味ください。
…なんだかジャッジの日記を書いてるんだかグルメの日記を書いてるんだかわからなくなってきましたね。
しかしそんな美味い飯を食いながらも、ジャッジが4人も揃えばやっぱり頭の中はマジックで一杯カンファレンスの延長戦、一週間後に迫ったグランプリ京都のことや、イベント運営に関する特殊技能について、何時間も語り続けて夜が更けていくのでした。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
そしてその前に、グランプリ京都に参加される方は、今週末に京都でお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○09/10土 『グランプリ京都』
○09/11日 『グランプリ京都』
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第4回です。
さて今回は、先週末の土曜日に名古屋の大須で行われたジャッジカンファレンスというものに参加してきましたので、そのお話をします。
ジャッジカンファレンスとは、ざっくり言えばジャッジの勉強会です。
ジャッジがイベント運営以外で複数人が集まり、ノウハウを共有するためのセミナーやコミュニティ形成のための会議などを行うものです。
さてこのジャッジカンファレンス、ここ数年でその内容が大きく変化しています。
日本でジャッジカンファレンスが行われ始めたのは3年ほど前で、主にグランプリに際して行われてきました。しかしそのため参加できるのはグランプリに来ているジャッジだけであり、地方のコミュニティを支えてくれているけれどグランプリには来ない・来られないジャッジが参加できないという問題を抱えていました。
そこで今年は、できるだけ多くのジャッジが参加できるように変化しました。大きなイベントにジャッジが遠征するではなく、地域ごとにそこに住むジャッジが集まれるよう、日本をいくつものエリアに区切って行うエリアカンファレンスという形式になりました。
今回は東海エリアカンファレンスとして、愛知・岐阜・三重からジャッジ約15名が名古屋大須に集まったというわけです。
そんな東海エリアカンファレンスは、まったりとした雰囲気で進行していました。
昨年までは、競技性の高いイベントを前提としたテーマが多かったのですが、今年は地元のレベル1ジャッジを主眼としています。そのため、地域のジャッジの活動状況を確認したり、地元でジャッジを増やすための方策を考えたりといったテーマで話し合いが行われました。
(もしこの日記を読んでジャッジに興味を持ってくれた人がいたら声をかけてくださいね!)
地域のジャッジが一同に会することは実はあまりなく、レベル1ジャッジだと他の地区のジャッジと交流が無いこともありますが、今回がレベル1ジャッジ同士の交流の場にもなっていたようです。
いつもジャッジとしてお世話になっているカードショップの店員さんもレベル1ジャッジとして参加していたのでちょっぴり緊張したり。
僕自身も久しぶりに会った人や初めて会った人がいて、またジャッジとしての親交の輪を広げることができました。
また、カンファレンスの参加者には、ジャッジ褒章フォイルも配布されました。
滅びはまだ4枚揃っていなかったので結構嬉しい。
そしてジャッジカンファレンスが終わったら、今回のために名古屋を訪れた日本の地域コーディネーター(日本のジャッジのまとめ役)を連れて4人で鶴舞のステーキ屋に向かいます。
STEAKEYE【ステーキアイ】
http://www.steak-eye.com/index.html
http://jouhou.nagoya/steak-eye/
看板料理となっている熟成肉のステーキは、脂が弾ける派手なステーキではなく、しっとりとした肉の旨みをゆっくり味わうことのできる上品な仕上がり。
アラカルトメニューも丁寧な仕事で悉くが美味く、何を頼んでも外れません。
僕のお気に入りは、野菜と肉の旨みが見事に調和した優しくも力強いポトフと、肉とガーリックのパンチがガツンと腹に響くガーリックライスです。
ぜひ一度ご賞味ください。
…なんだかジャッジの日記を書いてるんだかグルメの日記を書いてるんだかわからなくなってきましたね。
しかしそんな美味い飯を食いながらも、ジャッジが4人も揃えばやっぱり頭の中はマジックで一杯カンファレンスの延長戦、一週間後に迫ったグランプリ京都のことや、イベント運営に関する特殊技能について、何時間も語り続けて夜が更けていくのでした。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
そしてその前に、グランプリ京都に参加される方は、今週末に京都でお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○09/10土 『グランプリ京都』
○09/11日 『グランプリ京都』
ジャッジといえばイベントだろう!
2016年9月1日
こんばんは、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第3回です。
さて、先週の木曜日(先週の木曜日!)はルールの話をしたのですが、それを読んだ他のジャッジから
「ジャッジといえばイベントだろう!」
とのお声をいただきましたので、今週はイベント運営についてお話ししましょう。
あんなに疲れるイベント運営の何が楽しいのか、僕の考えをお話しします。
イベントを運営する楽しさは、一言でいえば「学園祭」でしょうか。
自分の好きなものに関して、参加者に楽しんでもらえる企画を、仲の良い仲間と一緒に実行していく、青春の味ですね。
店舗の小さなイベントなら自分が中心となって、グランプリなどの大きなイベントならチームの一員として、満足度の高いイベントをプレイヤーに提供するという目標を成し遂げていくことに、やりがいを感じます。
仲間と一緒にというのは重要なポイントで、目的を共有してともにイベントを運営する中で、日本中に世界中にジャッジの友人ができます。
満足度の高いイベントというのはただプレイヤーに迎合するというわけではありません。例えば競技性の高いイベントでは、正々堂々と全力を尽くせる雰囲気も、またプレイヤー満足度のひとつの形と言えます。
ジャッジはそんな雰囲気を演出するために、朝の挨拶から始まって様々な面で工夫をしています。ジャッジを呼ばれたときの対応もそのひとつです。難しいルールの質問をうまく説明できて納得してもらえたときはやっぱり嬉しいものですし、逆にうまく説明できなかったときは次はもっとうまくやろうと改善点を探します。
一方で、飯を食うため生きていくために本業でやっている仕事とは何が違うかと考えると、マジックという自分の大好きなことに関連してやりがいを感じられるということでしょうか。
仕事は仕事で仲間と協力しますし工夫しますしやりがいも感じますが、どうしてもやりたいことよりもやるべきことの方を強く感じてしまいます。自分が本当にやりたいことを仕事にできている人は多くないですし、また趣味を仕事にすると好きだったものを好きではなくなってしまうという話をよく聞きます。
ジャッジはあくまで趣味の延長であり完全な仕事ではない故に、ジャッジとしてイベントを運営しているときはやりたいこととやるべきことが一致しており、まるで幼い頃に夢見た理想の仕事に就いているかのように、あるいは学生時代の学園祭のように、頑張ることが心地よく感じられます。
(店舗関係者など仕事としてジャッジをしている人がこのあたりをどう感じているのかは、僕も気になるところではあります。)
ジャッジとしてイベントを運営することは、プレイヤーとはまた一味違ったマジックの楽しみ方を教えてくれています。
ただの趣味ではなく完全な仕事でもない、この絶妙な距離感が、ジャッジという特異な立ち位置の魅力であり、終わらない青春を過ごしているのだと、僕は考えています。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○09/04日 PPTQ霊気紛争-マナソース和歌山
http://www.manasource.net/page/24
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第3回です。
さて、先週の木曜日(先週の木曜日!)はルールの話をしたのですが、それを読んだ他のジャッジから
「ジャッジといえばイベントだろう!」
とのお声をいただきましたので、今週はイベント運営についてお話ししましょう。
あんなに疲れるイベント運営の何が楽しいのか、僕の考えをお話しします。
イベントを運営する楽しさは、一言でいえば「学園祭」でしょうか。
自分の好きなものに関して、参加者に楽しんでもらえる企画を、仲の良い仲間と一緒に実行していく、青春の味ですね。
店舗の小さなイベントなら自分が中心となって、グランプリなどの大きなイベントならチームの一員として、満足度の高いイベントをプレイヤーに提供するという目標を成し遂げていくことに、やりがいを感じます。
仲間と一緒にというのは重要なポイントで、目的を共有してともにイベントを運営する中で、日本中に世界中にジャッジの友人ができます。
満足度の高いイベントというのはただプレイヤーに迎合するというわけではありません。例えば競技性の高いイベントでは、正々堂々と全力を尽くせる雰囲気も、またプレイヤー満足度のひとつの形と言えます。
ジャッジはそんな雰囲気を演出するために、朝の挨拶から始まって様々な面で工夫をしています。ジャッジを呼ばれたときの対応もそのひとつです。難しいルールの質問をうまく説明できて納得してもらえたときはやっぱり嬉しいものですし、逆にうまく説明できなかったときは次はもっとうまくやろうと改善点を探します。
一方で、飯を食うため生きていくために本業でやっている仕事とは何が違うかと考えると、マジックという自分の大好きなことに関連してやりがいを感じられるということでしょうか。
仕事は仕事で仲間と協力しますし工夫しますしやりがいも感じますが、どうしてもやりたいことよりもやるべきことの方を強く感じてしまいます。自分が本当にやりたいことを仕事にできている人は多くないですし、また趣味を仕事にすると好きだったものを好きではなくなってしまうという話をよく聞きます。
ジャッジはあくまで趣味の延長であり完全な仕事ではない故に、ジャッジとしてイベントを運営しているときはやりたいこととやるべきことが一致しており、まるで幼い頃に夢見た理想の仕事に就いているかのように、あるいは学生時代の学園祭のように、頑張ることが心地よく感じられます。
(店舗関係者など仕事としてジャッジをしている人がこのあたりをどう感じているのかは、僕も気になるところではあります。)
ジャッジとしてイベントを運営することは、プレイヤーとはまた一味違ったマジックの楽しみ方を教えてくれています。
ただの趣味ではなく完全な仕事でもない、この絶妙な距離感が、ジャッジという特異な立ち位置の魅力であり、終わらない青春を過ごしているのだと、僕は考えています。
今週は以上です。
また来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○09/04日 PPTQ霊気紛争-マナソース和歌山
http://www.manasource.net/page/24
ジャッジといえばルール!ルールといえばジャッジ!
2016年8月25日
こんばんは、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第2回です。
最初に「毎週木曜日に投稿します」なんて言ったばかりなのに、第2回から早速4日も遅れてしまいましたが、遅れても投稿日を捏造できるのがDiaryNoteの良いところですね。
さて、先週は挨拶だけだったので、実質初回となる今週はどんなテーマで書いたものかと何名かの友人に何を書いてほしいか聞いてみたところ…
「ジャッジといえばルール!
ルールといえばジャッジ!」
との声があったので、今週はジャッジらしく(?)マジックのゲームルールについてお話しします。
僕たちジャッジは、一体何が楽しくてゲームルールに詳しくなっているのでしょう。
僕のゲームルールの楽しみ方を紹介します。
マジックのゲームルールの一番大元になっている「総合ルール」は、とても複雑で膨大だという話をよく聞きます。
公式サイト:http://mtg-jp.com/rules/docs/CompRules_j.html#
「総合ルール」とは、ゲームがどのように進行しカードがどのように機能するのかを決めるルールです。総合ルールがちゃんとしていないと、ゲーム上の処理が曖昧になって問題が起きてしまいます。
確かに総合ルールはとても膨大で、一から十まで全部丸暗記するのはとても無理です。
でも複雑かというと、僕はそうとは考えていません。
マジックのルールはとても頭の良い人たちが考えて作っており、それぞれのルールが存在することには明確な理由があり、綺麗に整理されています。その結果、普段のゲームでは使わないようなものすごく詳細なことまで大量に厳密に明記されているため、詳しくない人にとっては複雑そうに見えるだけです。
総合ルールがきちんと整備されているということは、他のTCGに比べて特筆されるマジックのポイントのひとつです。
僕は裏設定オタですので、そんなルールを勉強する過程で、今まで知らなかった細かいルールを発見したり、今まで漠然としか意識していなかったルールを再確認したりして、そのルールが何故存在しているのかを考えることを楽しんでいます。
具体的な例を挙げましょう。
《帰化》で《安らかなる眠り》を破壊した場合、《帰化》は解決後に墓地と追放のどちらに置かれるでしょうか?
モダンやレガシーでよくある状況なので、ルールに詳しい人なら知っているかもしれません。
答えは、《帰化》は墓地へ置かれます。
では何故そうなるのでしょうか。
模範解答を示しますと、呪文として唱えられたカードは、解決の手順の一番最後に墓地へ置かれるというルールがあるからです。
参考:http://mtg-jp.com/rules/docs/CompRules_j.html#r608.2k
《帰化》の解決に際しての行動で《安らかなる眠り》が破壊されて戦場からなくなり、そして解決の最後に《帰化》が墓地へ置かれるので、《帰化》は《安らかなる眠り》の置換効果の影響を受けることはありません。
普段はカードを呪文として唱えたらそのまま墓地へ置くことも多く「解決されたら墓地へ置く」で問題はないのですが、実は呪文の解決はいくつかのステップがあります。
ではではもう一歩踏み込んで、何故そのようなルールが存在するのかを考えてみましょう。
ここからは妄想が膨らんでいきます。
ぱっと思いつくのは、単純に、それが自然ということでしょうか。
呪文はカードに書いてあることを行わなければならないのだから、最後までスタックに置いてあるのが自然な姿でしょう。最後までスタックになかったら、その後の処理を墓地を見ながら行わなければならなくなります。解決の途中で複雑な処理を含むカードは特に、最後までスタックの上に残っていないと処理を間違えてしまうかもしれません。
しかしまだパンチが弱いですね。
もっと決定的な理由はないかと考えて、仮に「解決の最初にスタックから墓地へ置く」というルールだったら困ることがないかとGathererを探してみましょう…
ありました。
こんなカードは困りそうです。
仮に「呪文はその解決の手順の最初にスタックから取り除き墓地へ置く」というルールの世界線で《過ぎ去った季節》を唱えたらどうなるか考えてみましょう。
《過ぎ去った季節》の解決が始まります。
まず最初にスタック上の《過ぎ去った季節》を墓地へ置きましょう。
続いて墓地から手札に戻すカードを選びますが…、おっと、今使った《過ぎ去った季節》が既に墓地にありますね。これは手札に戻せます。君は《過ぎ去った季節》を手札に戻してもいいし、他のカードを戻してもいい。
そして《過ぎ去った季節》自身をライブラリーボトムに置こうとしますが…、おやおや、《過ぎ去った季節》はもうスタックに存在しません。できないので無視しましょう。この無意味な最後の一文の存在意義に疑問を抱きます。
※領域を移動したカードは、物理的には同じものでも、ルール的には「違うもの」として扱われます。
つまり仮のルールの世界線では、《過ぎ去った季節》はデメリット無しで、墓地からカードを何度でも回収できる、とんでもない爆アド呪文になってしまいます!過ぎ去れよ季節!
…と、ここらへんまで妄想を膨らませて、「ああなるほどやっぱり呪文が解決の最後に墓地に置かれることは必要なことなんだなぁ。」と納得してスッキリする、それが僕のルールの楽しみ方です。
いかがでしたでしょうか、あまり外には出さないジャッジの楽しみ方のひとつとして紹介になっていれば幸いです。
もっとも、ルール好きなジャッジにも楽しみ方は色々ありますので、別のジャッジはまた別の楽しみ方でルールに接していますが、それはいずれまた。
今週は以上です。
今度こそ、また来週の木曜日にお会いしましょう。
「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」
ということを広めたくて始めた日記の第2回です。
最初に「毎週木曜日に投稿します」なんて言ったばかりなのに、第2回から早速4日も遅れてしまいましたが、遅れても投稿日を捏造できるのがDiaryNoteの良いところですね。
さて、先週は挨拶だけだったので、実質初回となる今週はどんなテーマで書いたものかと何名かの友人に何を書いてほしいか聞いてみたところ…
「ジャッジといえばルール!
ルールといえばジャッジ!」
との声があったので、今週はジャッジらしく(?)マジックのゲームルールについてお話しします。
僕たちジャッジは、一体何が楽しくてゲームルールに詳しくなっているのでしょう。
僕のゲームルールの楽しみ方を紹介します。
マジックのゲームルールの一番大元になっている「総合ルール」は、とても複雑で膨大だという話をよく聞きます。
公式サイト:http://mtg-jp.com/rules/docs/CompRules_j.html#
「総合ルール」とは、ゲームがどのように進行しカードがどのように機能するのかを決めるルールです。総合ルールがちゃんとしていないと、ゲーム上の処理が曖昧になって問題が起きてしまいます。
確かに総合ルールはとても膨大で、一から十まで全部丸暗記するのはとても無理です。
でも複雑かというと、僕はそうとは考えていません。
マジックのルールはとても頭の良い人たちが考えて作っており、それぞれのルールが存在することには明確な理由があり、綺麗に整理されています。その結果、普段のゲームでは使わないようなものすごく詳細なことまで大量に厳密に明記されているため、詳しくない人にとっては複雑そうに見えるだけです。
総合ルールがきちんと整備されているということは、他のTCGに比べて特筆されるマジックのポイントのひとつです。
僕は裏設定オタですので、そんなルールを勉強する過程で、今まで知らなかった細かいルールを発見したり、今まで漠然としか意識していなかったルールを再確認したりして、そのルールが何故存在しているのかを考えることを楽しんでいます。
具体的な例を挙げましょう。
《帰化》で《安らかなる眠り》を破壊した場合、《帰化》は解決後に墓地と追放のどちらに置かれるでしょうか?
帰化/Naturalize (1)(G)
インスタント
アーティファクト1つかエンチャント1つを対象とし、それを破壊する。
安らかなる眠り/Rest in Peace (1)(W)
エンチャント
安らかなる眠りが戦場に出たとき、すべての墓地にあるすべてのカードを追放する。
カードかトークンがいずれかの領域からいずれかの墓地に置かれる場合、代わりにそれを追放する。
モダンやレガシーでよくある状況なので、ルールに詳しい人なら知っているかもしれません。
答えは、《帰化》は墓地へ置かれます。
では何故そうなるのでしょうか。
模範解答を示しますと、呪文として唱えられたカードは、解決の手順の一番最後に墓地へ置かれるというルールがあるからです。
参考:http://mtg-jp.com/rules/docs/CompRules_j.html#r608.2k
《帰化》の解決に際しての行動で《安らかなる眠り》が破壊されて戦場からなくなり、そして解決の最後に《帰化》が墓地へ置かれるので、《帰化》は《安らかなる眠り》の置換効果の影響を受けることはありません。
普段はカードを呪文として唱えたらそのまま墓地へ置くことも多く「解決されたら墓地へ置く」で問題はないのですが、実は呪文の解決はいくつかのステップがあります。
ではではもう一歩踏み込んで、何故そのようなルールが存在するのかを考えてみましょう。
ここからは妄想が膨らんでいきます。
ぱっと思いつくのは、単純に、それが自然ということでしょうか。
呪文はカードに書いてあることを行わなければならないのだから、最後までスタックに置いてあるのが自然な姿でしょう。最後までスタックになかったら、その後の処理を墓地を見ながら行わなければならなくなります。解決の途中で複雑な処理を含むカードは特に、最後までスタックの上に残っていないと処理を間違えてしまうかもしれません。
しかしまだパンチが弱いですね。
もっと決定的な理由はないかと考えて、仮に「解決の最初にスタックから墓地へ置く」というルールだったら困ることがないかとGathererを探してみましょう…
ありました。
こんなカードは困りそうです。
過ぎ去った季節 (4)(G)(G)
ソーサリー
あなたの墓地から点数で見たマナ・コストが互いに異なるカードを望む枚数あなたの手札に戻す。過ぎ去った季節をオーナーのライブラリーの一番下に置く。
仮に「呪文はその解決の手順の最初にスタックから取り除き墓地へ置く」というルールの世界線で《過ぎ去った季節》を唱えたらどうなるか考えてみましょう。
《過ぎ去った季節》の解決が始まります。
まず最初にスタック上の《過ぎ去った季節》を墓地へ置きましょう。
続いて墓地から手札に戻すカードを選びますが…、おっと、今使った《過ぎ去った季節》が既に墓地にありますね。これは手札に戻せます。君は《過ぎ去った季節》を手札に戻してもいいし、他のカードを戻してもいい。
そして《過ぎ去った季節》自身をライブラリーボトムに置こうとしますが…、おやおや、《過ぎ去った季節》はもうスタックに存在しません。できないので無視しましょう。この無意味な最後の一文の存在意義に疑問を抱きます。
※領域を移動したカードは、物理的には同じものでも、ルール的には「違うもの」として扱われます。
つまり仮のルールの世界線では、《過ぎ去った季節》はデメリット無しで、墓地からカードを何度でも回収できる、とんでもない爆アド呪文になってしまいます!過ぎ去れよ季節!
…と、ここらへんまで妄想を膨らませて、「ああなるほどやっぱり呪文が解決の最後に墓地に置かれることは必要なことなんだなぁ。」と納得してスッキリする、それが僕のルールの楽しみ方です。
いかがでしたでしょうか、あまり外には出さないジャッジの楽しみ方のひとつとして紹介になっていれば幸いです。
もっとも、ルール好きなジャッジにも楽しみ方は色々ありますので、別のジャッジはまた別の楽しみ方でルールに接していますが、それはいずれまた。
今週は以上です。
今度こそ、また来週の木曜日にお会いしましょう。
ジャッジ活動は楽しいことなのです
2016年8月18日初めまして、名古屋でMTGのL2ジャッジをしている「ふみ」です。
ツイッター:https://twitter.com/MTG2384
最初に軽く自己紹介を。
もともとはルール好きな頭でっかちプレイヤーでしたが、2011年春にひょんなことからジャッジに興味を持ち、2011年8月にレベル1、2012年7月にレベル2を合格して、それからずっとジャッジ活動にのめり込み続けています。
現在は、普段は主に名古屋を中心として岐阜や三重あたりまでのお店のPPTQでジャッジをしています。国内のグランプリには2012年以降ほぼ毎回ジャッジとして参加していて、また最近は関東や関西の大きなイベントにもちょくちょくお邪魔しています。ここ1年で60日くらいは競技イベントでジャッジをしてるので、ジャッジ活動頻度ではおそらく日本でかなり上位を争っている一人だと思います。
過去にもDiaryNoteで日記を書いていたのですが、もう何年もまともに更新していなかったですし、まともに更新していなかった間にコミュニティでの立場も結構変わりましたので、心機一転新しいページを作って、ジャッジとしての視点から日記を書いていくことにしました。
さて、名古屋でPPTQをはじめとしたMTGのイベントにたくさん関わるようになって、しばらく経ちました。ありがたいことに地元のプレイヤーにはそこそこ顔を覚えていただき、イベントで顔を合わせた際には「今日もジャッジお疲れ様です」「いつもジャッジは大変ですね」なんてよく声をかけてもらえるようになりました。
いつもありがとうございます。
…でもちょこっとだけ違うんです。
たしかに体力的には疲れます。
でも僕にとってジャッジ活動することは辛くて苦しいものではないのです。
ジャッジとして活動する中で、ルールについて会話したり、イベントを運営したり、色んな地域に遠征したりすることは、僕にとって楽しいことなのです。
もっともこれは僕個人の考えであり、他のジャッジが皆そうだとは限りません。
単に仕事やバイトとして割り切ってジャッジ活動をしている人もいます。
ただ、僕がジャッジ活動をしているのをプレイヤーから見て「ジャッジはブラック企業っぽい」なんてイメージが付いてしまうのはよろしくないな、と考え始めました。
そこで、ジャッジとしてMTGに関わる中で経験した楽しいことを紹介していく日記を始めます。
書く内容は「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」で、面白いルールとか、参加したイベントとか、イベント外でジャッジとして動いたこととか、その他時事ネタとかです。ジャッジではない人にジャッジの楽しみ方を紹介するものなので、固い話や細かい話は避けます。
もし取り上げてほしい話題があれば、言ってもらえればテーマとして採用するかもしれません。
イメージとしては、何年か前に公式で連載していた認定ジャッジによる週替わりコラムの緩いバージョンと思ってください。
できるだけ毎週木曜日の夜に投稿していきたいと思っています。
おっと、日記の題名はまだ仮題ですので、そのうち良いものが思い付いたら変更します。
もしこれからの日記を読んでジャッジに興味を持ってくれた方がいましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。
こちら側へようこそ、とりあえずおいしいご飯でも食べつつお話ししましょう。
とりあえず今週はこれだけです。
みなさん改めてよろしくお願いします。
それではまた来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○08/20土 PPTQ霊気紛争-TOY&HOBBY美嶋屋
https://twitter.com/toys3408/status/763317988334313473
ツイッター:https://twitter.com/MTG2384
最初に軽く自己紹介を。
もともとはルール好きな頭でっかちプレイヤーでしたが、2011年春にひょんなことからジャッジに興味を持ち、2011年8月にレベル1、2012年7月にレベル2を合格して、それからずっとジャッジ活動にのめり込み続けています。
現在は、普段は主に名古屋を中心として岐阜や三重あたりまでのお店のPPTQでジャッジをしています。国内のグランプリには2012年以降ほぼ毎回ジャッジとして参加していて、また最近は関東や関西の大きなイベントにもちょくちょくお邪魔しています。ここ1年で60日くらいは競技イベントでジャッジをしてるので、ジャッジ活動頻度ではおそらく日本でかなり上位を争っている一人だと思います。
過去にもDiaryNoteで日記を書いていたのですが、もう何年もまともに更新していなかったですし、まともに更新していなかった間にコミュニティでの立場も結構変わりましたので、心機一転新しいページを作って、ジャッジとしての視点から日記を書いていくことにしました。
さて、名古屋でPPTQをはじめとしたMTGのイベントにたくさん関わるようになって、しばらく経ちました。ありがたいことに地元のプレイヤーにはそこそこ顔を覚えていただき、イベントで顔を合わせた際には「今日もジャッジお疲れ様です」「いつもジャッジは大変ですね」なんてよく声をかけてもらえるようになりました。
いつもありがとうございます。
…でもちょこっとだけ違うんです。
たしかに体力的には疲れます。
でも僕にとってジャッジ活動することは辛くて苦しいものではないのです。
ジャッジとして活動する中で、ルールについて会話したり、イベントを運営したり、色んな地域に遠征したりすることは、僕にとって楽しいことなのです。
もっともこれは僕個人の考えであり、他のジャッジが皆そうだとは限りません。
単に仕事やバイトとして割り切ってジャッジ活動をしている人もいます。
ただ、僕がジャッジ活動をしているのをプレイヤーから見て「ジャッジはブラック企業っぽい」なんてイメージが付いてしまうのはよろしくないな、と考え始めました。
そこで、ジャッジとしてMTGに関わる中で経験した楽しいことを紹介していく日記を始めます。
書く内容は「ジャッジってこんなこと考えて楽しんでるんだよ」で、面白いルールとか、参加したイベントとか、イベント外でジャッジとして動いたこととか、その他時事ネタとかです。ジャッジではない人にジャッジの楽しみ方を紹介するものなので、固い話や細かい話は避けます。
もし取り上げてほしい話題があれば、言ってもらえればテーマとして採用するかもしれません。
イメージとしては、何年か前に公式で連載していた認定ジャッジによる週替わりコラムの緩いバージョンと思ってください。
できるだけ毎週木曜日の夜に投稿していきたいと思っています。
おっと、日記の題名はまだ仮題ですので、そのうち良いものが思い付いたら変更します。
もしこれからの日記を読んでジャッジに興味を持ってくれた方がいましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。
こちら側へようこそ、とりあえずおいしいご飯でも食べつつお話ししましょう。
とりあえず今週はこれだけです。
みなさん改めてよろしくお願いします。
それではまた来週の木曜日にお会いしましょう。
~~~~~~~~
今週末の予定です。よろしくお願いします。
○08/20土 PPTQ霊気紛争-TOY&HOBBY美嶋屋
https://twitter.com/toys3408/status/763317988334313473

![[トーナメントレポート] BIG MAGIC Open Vol.10 Sunday Legacy デッキチェックチーム](http://diarynote.jp/data/blogs/m/20180508/112203_201805082343042007_1.jpg)
![[トーナメントレポート] BIG MAGIC Open Vol.10 Sunday Legacy デッキチェックチーム](http://diarynote.jp/data/blogs/m/20180508/112203_201805082343042007_2.jpg)